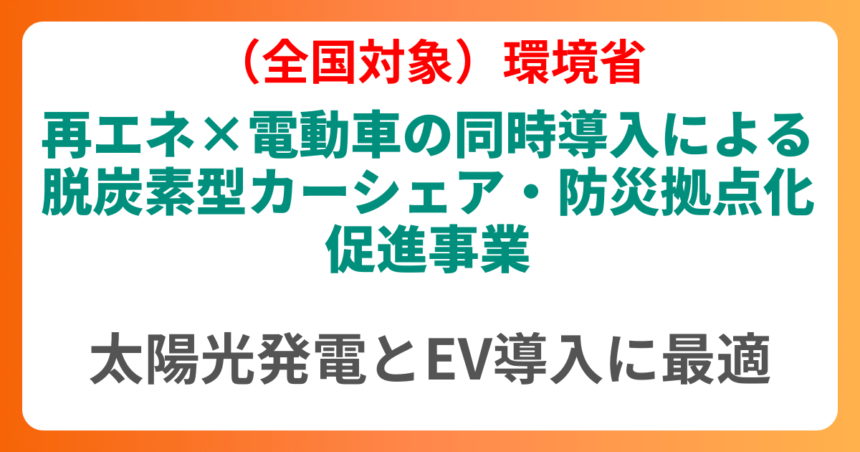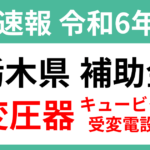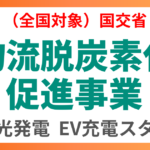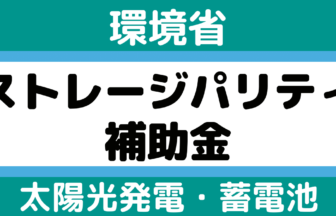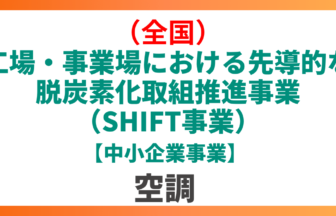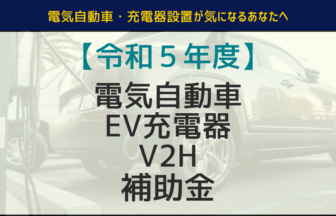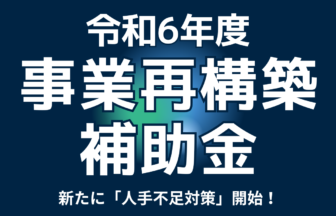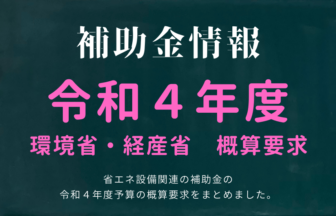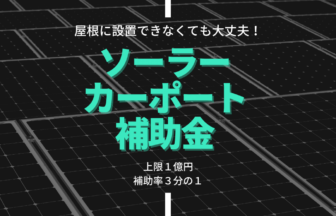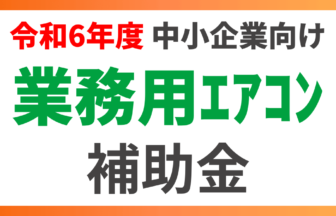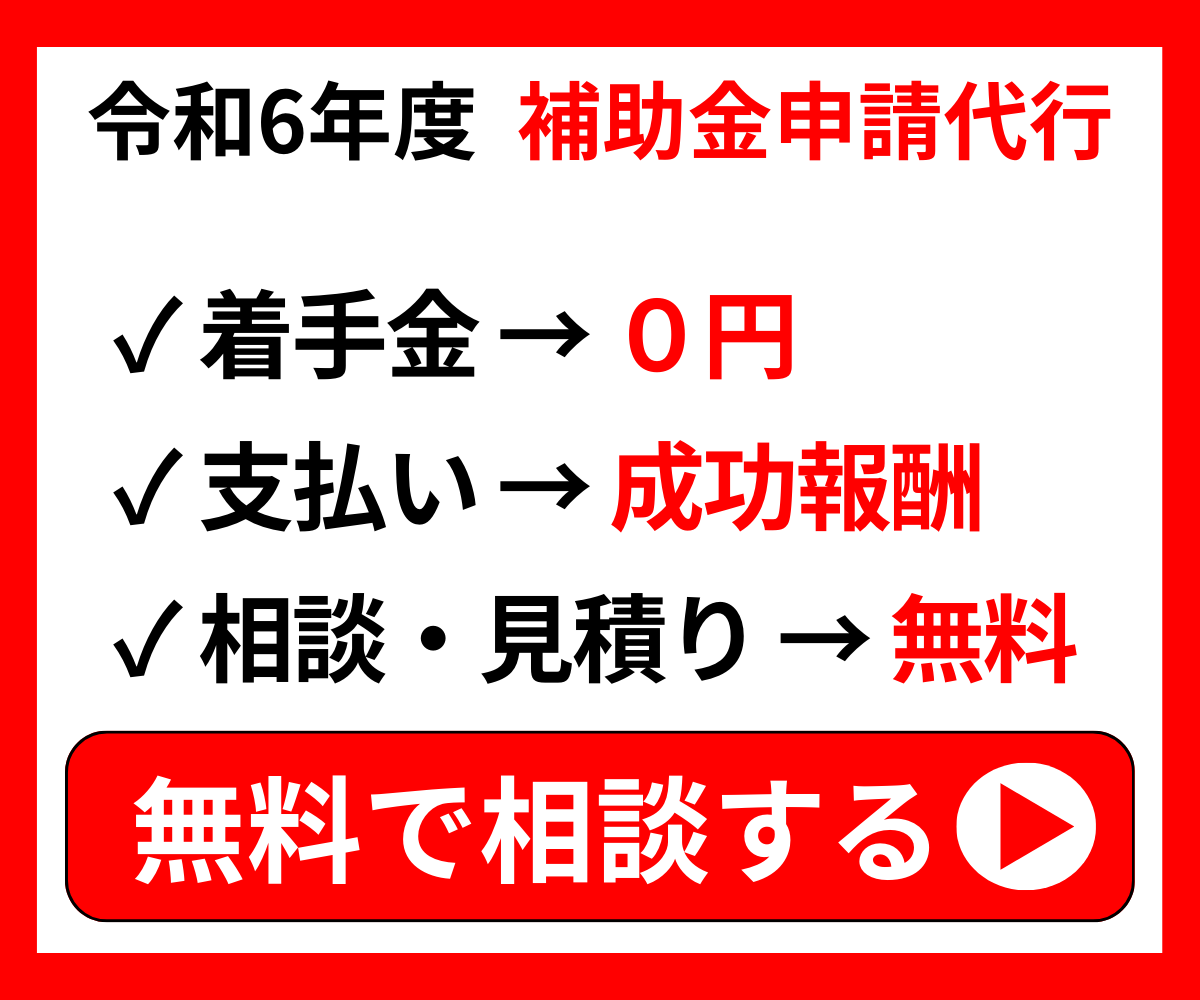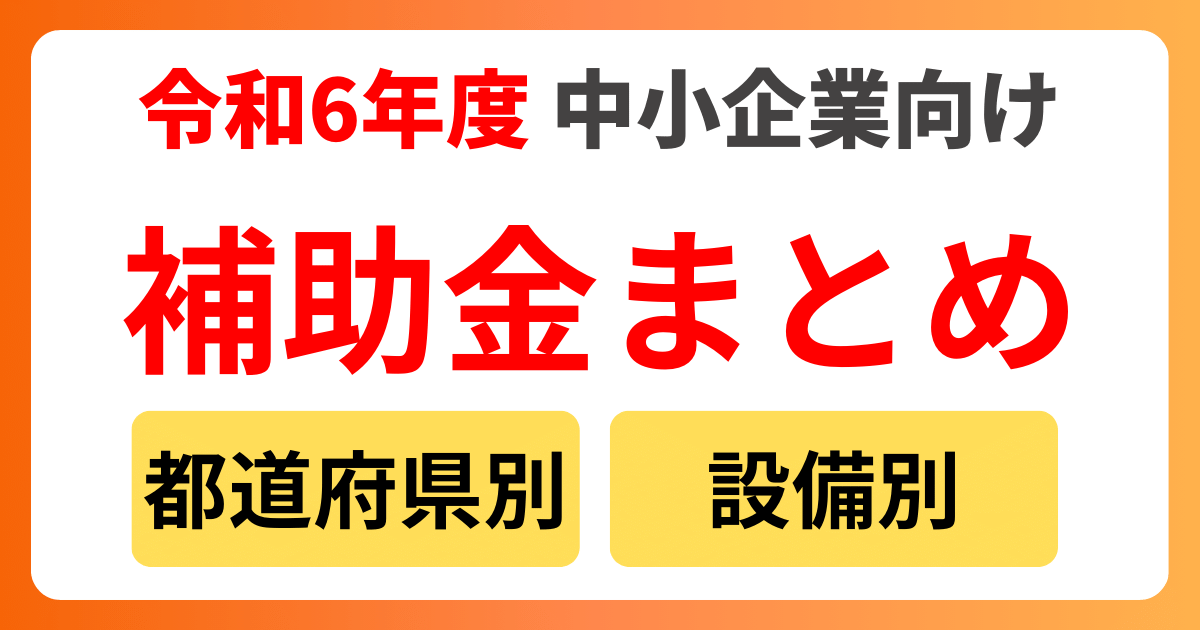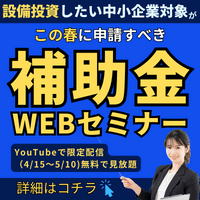再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業とは、再生可能エネルギー発電設備と電気自動車等を同時導入し、地域住民等向けにシェアリングするとともに、充放電設備/外部給電気の導入及び災害時における活用を行う事業に要する経費の一部を補助する、環境省の補助金です。
つまり、【「再エネ」「電気自動車」「充放電設備」を施設に導入し、電気自動車は普段からシェアし、災害時には電気自動車の充電設備を地域に開放する】ことが補助金の条件となります。
一見、難しそうではありますが、これが実現できると、脱炭素化・停電対策・社員の福利厚生・地域貢献を一気に叶えることができ、企業価値が上がることとなります。
また、各設備を単独で見た場合、どれも今後の企業にとって設置が不可欠になるものばかりです。
それであるならば、一気に補助金を使って設置をするのも検討アリだと思われます。
それでは、この補助金について、詳しく見ていきましょう。
カーシェアってどうなの?
「せっかく経費で購入した電気自動車をシェアするのは・・・」という不安もあると思います。
補助金が対象となるカーシェアは、4パターンあり、そのうち民間企業のシェア方法は次のうちの2パターンです。
- 社用車を従業員とシェアする
- 社用車を他の企業や地方自治体とシェアする
他の企業や地方自治体とシェアすることは、なかなか難しいかもしれませんが、従業員とのシェアは社内で済む話であるため、ハードルが低いのではないでしょうか。
社用車の従業員シェアは、EVシフトが進んでいるヨーロッパではよくある話です。
これを実施すると、従業員は通勤の車を購入する必要がなくなります。
また、普段は電車通勤で、休日に家族で出かけたいときに車をレンタルする必要もなくなります。
実際にこれを社内の制度として導入する場合、車両保険の扱いや、万が一の事故の際の対応などのルールを決める必要がありますが、社用車を電気自動車に変え、通勤車が減ることにより、企業としてCO2削減を進めることが可能です。
太陽光発電の設置容量には注意が必要
太陽光発電の設置容量は、同時に購入する電気自動車により決まります。
まず、この補助金を活用するためには、電気自動車を1台以上購入しなければいけません。
その上で、購入する電気自動車の「走行による想定年間消費電力量をまかなえる容量」以上にする必要があります。
前提として、太陽光発電は自家消費のみ対象です。
この「走行による想定消費電力量」は、既定の計算式で算出します。
【計算式】
設備容量(kW・台)=年間走行距離(km/年)×電費(kWh/km)×申請車両台数(台)÷地域別補正係数(kWh/年/kW)
となります。
年間走行距離は想定している走行距離となり、電費はカタログ値を使います。地域別補正係数は都道府県により異なりますが、だいたい1.1~1.3の間の値となります。
既に太陽光発電を設置している場合、この計算式で算出される値以上であれば補助金の申請は可能です。
では、太陽光発電が設置できない施設、設置しても必要な容量を発電するほどの容量が設置できない場合は、申請できないかというとそうではありません。
その場合、環境省が認定した一覧から「再エネ電力メニューを導入」するならば申請可となります(環境省が認定する再エネ電力メニュー一覧)。
気になる補助率は1/2となっており、他の国の補助率である4万円/kWと比べるとかなり補助額が多くなると思われます。また、太陽光発電単体での上限額は決まっていません。
自家消費の条件をクリアし、トータルの補助上限額1億円を超えなければOKです。
電気自動車はCEV補助金と比べてどちらがお得?
電気自動車の購入補助金として、CEV補助金が実施されています。
今回の補助金とCEV補助金はどちらがお得か比べてみましょう。
(今回の補助金名が長いので「カーシェア補助金」とさせてもらいます)
次の表は1台あたりの補助上限額となります。
| カーシェア補助金 | CEV補助金 | |
| 電気自動車 | 120万円 補助率1/3 | 最大85万円 |
| プラグインハイブリッド車 | 72万円 補助率1/3 | 最大55万円 |
ご覧の通り、今回の補助金の方が、CEV補助金よりも上限額が高いことがわかります。
また、カーシェアする際のルール次第となりますが、カーシェアする従業員に利用料として一部費用負担をしてもらえれば、さらに購入コストの負担を減らすことが可能です。
充電設備設置も充電インフラ補助金と比べて問題なし
充電設備についても充電インフラ補助金と比較して、十分な額となっています。
充電器設置については、かなり細かく分岐しますので割愛しますが、通常会社に設定する場合は「充電コンセント」か「普通充電器」となります。
どちらも、機器代、工事費ともに充電インフラと同等の金額が補助されます。
急速充電器設置の場合、出力が大きい機器の場合は充電インフラ補助金の方が補助額が多くなりそうですが、急速充電器を設置するケースはあまりないと思います。
補助金の内容
前置きが長くなりましたが、補助金の概要を表でお伝えします。
| 対象 | 民間企業・地方自治体など |
| 補助上限・補助率 | ・電気自動車:120万円/台・1/3 ・プラグインハイブリッド車72万円・1/3 ・再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備:1/2 ・再生可能エネルギー発電設備設置工事:1/2 ・外部給電器:50万円/台:1/3 ・V2H 充放電設備:75万円/台:1/2 ・V2H 充放電設備設置工事費:95万円/台・1/2 ・充電設備:7~300万円/台・1/2 ・充電設備設置工事費:95~140万円/台・1/2 |
| 合計の補助上限額 | 1億円 |
| 申請期間(R5年度) | ・3/24~6/30 ・8/1~10/31 ・12/1~1/31 ※2回目で予算超過のため募集なし |
| 執行団体 | 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 |
令和6年度は・・・
残念ながら現段階で実施されるか不明となります。
情報が入り次第追記してまいります。
この補助金は「太陽光発電」「電気自動車」「EV充電スタンド」の3つの設備設置が補助されます。
脱炭素化・電気代高騰対策の両方に有効な設備となり、かつ単独の設置に使える補助金よりも手厚い補助金ですので、一気に設置する予算があれば、トータルではかなりメリットが大きい補助金と言えます。
近隣エリアで、中小企業が使える補助金一覧
近隣エリアが出している補助金を探している場合は、エリア別の補助金や助成金の一覧をご覧ください。
本社や支店の事業所があれば、使える補助金が見つかります。
- 令和6年度版:全国の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:東京都の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:神奈川県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:千葉県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:埼玉県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:茨城県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:栃木県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:群馬県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:福島県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:新潟県の中小向け企業補助金・助成金の一覧
- 中小企業経営強化税制(税制優遇制度)で即時償却や税額控除
もしも見つからなかった場合や探すのが面倒な場合は、明電産業の無料相談をご利用ください。
【設備別】中小企業が使える補助金一覧
省エネや再エネ設備など、設備ごとに補助金を探している場合は、設備別の補助金や助成金の一覧をご覧ください。
本社や支店の事業所があれば、使える補助金が見つかります。
- 令和6年版:中小企業が省エネ・再エネ・畜エネ・創エネ設備に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業が太陽光発電設備に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業が蓄電池に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業がLED照明への交換に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業が業務用エアコン交換に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業が変圧器(キュービクル/受変電設備)に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業がEV・PHV用充電器に使える補助金・助成金一覧
- 中小企業経営強化税制(税制優遇制度)で即時償却や税額控除
もしも見つからなかった場合や探すのが面倒な場合は、明電産業グループの無料相談をご利用ください。
明電産業グループは、昭和23年創業(栃木県宇都宮市)の電設資材の商社です。
部材の仕入れも、施工(工事)も、補助金や税制優遇制度の申請代行もできます。
補助金を使って、設備の導入費用を削減したい場合は、まずはお気軽にご相談ください。
【事例紹介】補助金を使ったコスト削減
設備ごとに、補助金を使った事例を画像や動画付きで掲載しています。
きっとお役に立てると思いますので、ご覧ください。
補助金を使った場合の初期投資費用や投資回収期間を記載しています。
これから設備投資や補助金活用をご検討の場合は、ご覧ください。
明電産業グループでは、あなたの会社の脱炭素経営や環境対策、SDGs活動の取り組みを無料でPRします。
自社の活動をWEBサイトやSNSでPRしたいけど、自社では難しい場合はご連絡ください。
必要に応じてドローン撮影をおこないます。画像や動画素材はすべて無料で提供します。
中小企業のSDGs取り組み事例を募集します!
よくあるご質問(Q&A)のまとめ
明電産業グループでは、設備投資や補助金についてお客様からのご相談やご質問をいただきます。
太陽光発電設備/蓄電池/LED照明/省エネ空調/受変電設備(キュービクル)/EV充電器/税制優遇制度について、Q&Aをまとめていますのでご覧ください。
お客様からの「よくあるご質問」を見る
「よくあるご質問(Q&A)」で解決できない場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
明電産業グループの補助金申請の専任がお答えします。
設備の導入コストや投資の回収期間を大幅に削減したいなら、ご相談ください

法人企業が補助金を活用すれば、大幅なコストダウンができます。
明電産業グループは、昭和23年創業(栃木県宇都宮市)の電設資材の商社です。
当社では、設備の仕入れ・施工・補助金の申請まで一括で対応いたします。
補助金を使うことが前提なので、設備の導入コストを大幅に削減できます。
もしも次の内容に当てはまっていたら、補助金を検討してください。
- 設備導入に費用をかけたくない
- 補助金や助成金を探すのが面倒だ
- 施工や補助金申請など、まとめて依頼したい
- 補助金の実績があるところに頼みたい
- 補助金が決まるまでは、お金を払いたくない
補助金申請のポイントは、今すぐ準備をすることです。
理由は、補助金の予算が達成してしまうと受付終了となるからです。
明電産業グループの経験では、たったの3時間で早期終了した補助金もあります。
もしもあなたが、設備の導入コストを削減しつつ、業務の手間を省き、実績のある会社を選びたいのならまずはご相談ください。
ご自身で調べるより、ご相談いただいた方が早く見つけられます。
一緒に、あなたの会社で使える補助金を見つけましょう。