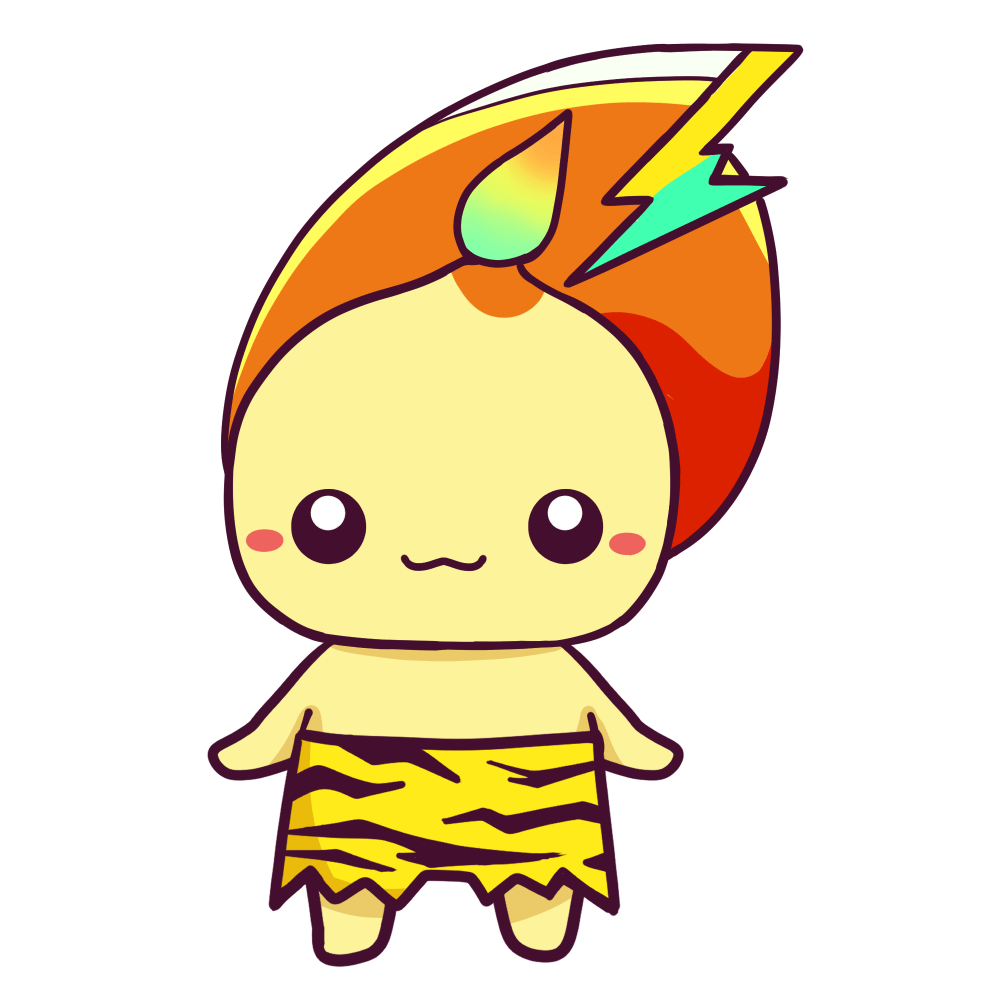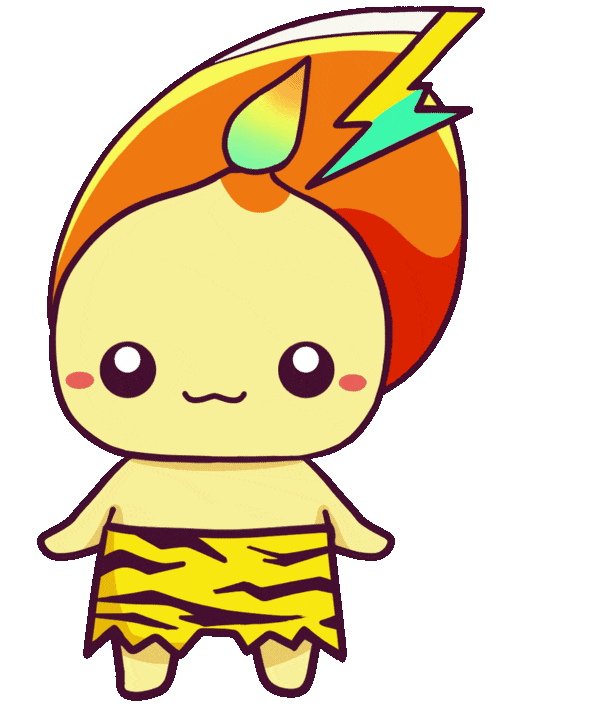企業向け太陽光発電の導入で失敗しないための注意点
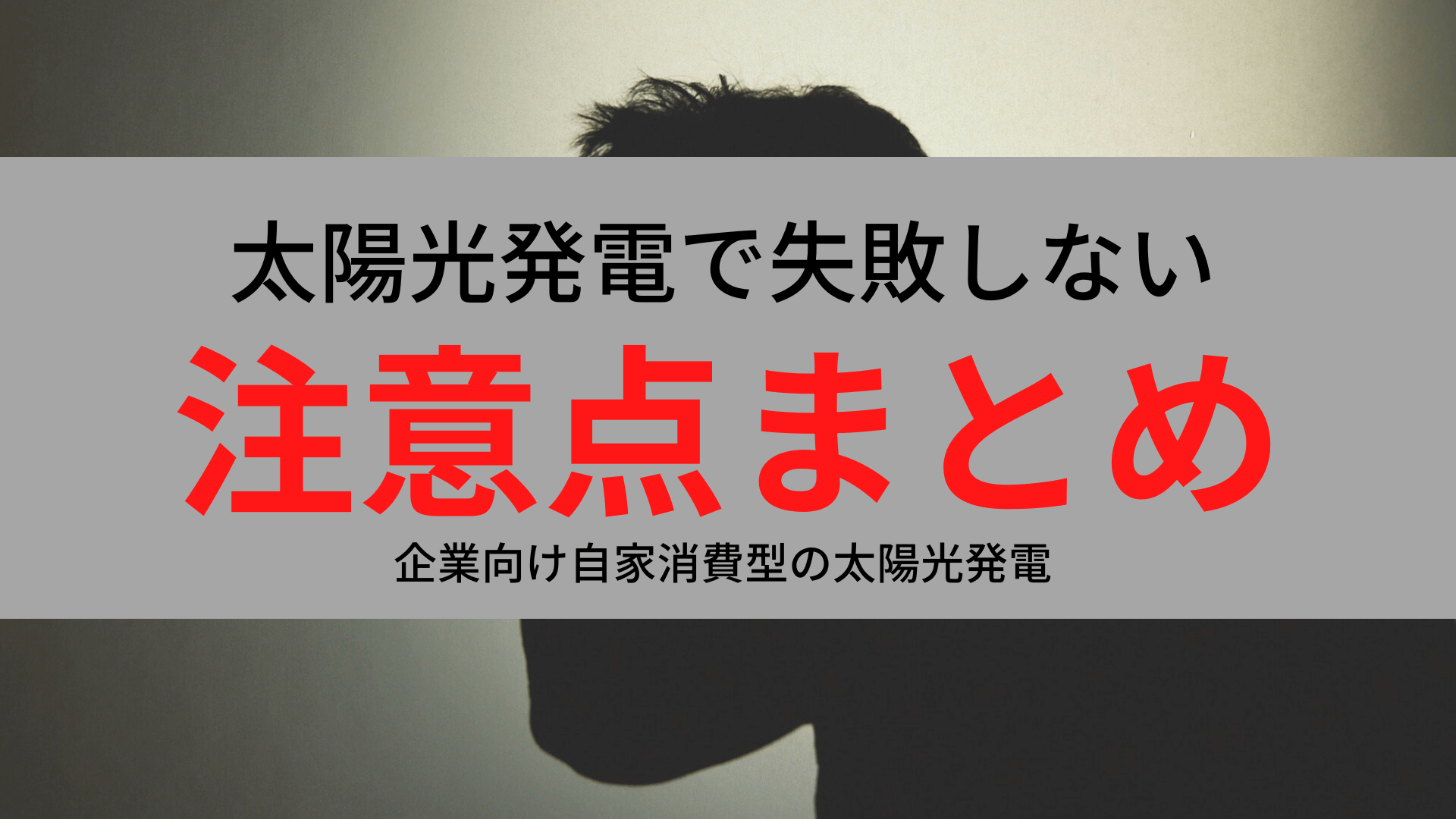
あなたの企業でも太陽光発電設備の導入を検討されていると思います。
とくに令和4年頃から、建物の屋上や敷地内に太陽光発電を設置している企業がとても増えてきました。
このページでは、企業が自家消費型の太陽光発電設備を導入するときの失敗事例や、失敗しないための注意点をまとめています。
<失敗してしまうポイント>
①導入するときの手続き(電力協議や申請)で失敗する
②補助金のことをよく理解していなくて失敗する
③構造計算や耐荷重確認をせずに導入して失敗する
④施工で必須となる「停電工事」で失敗する
⑤設置後に、保守管理維持で失敗する
注意点よりもまずは、「太陽光パネルを載せた場合の概算だけでも知りたい」という方は、
【レクチャー付き】補助金を使った太陽光発電シミュレーション(無料)を試す
失敗事例や導入するための注意ポイントをまとめたページがなかったので解説します。
太陽光発電設備の導入は、失敗事例を学んでからでも遅くありません。
明電産業/牛山電工は、昭和23年創業の電設資材の卸会社です。
補助金を使って企業の電気代削減をすることが得意で、補助金申請専門の部署があります。すでに令和5年度の補助金申請のサポートしています。
太陽光発電設備の導入で補助金の活用を考えていると思いますので、まずはこのページをご覧ください。
成功事例や補助金情報を知りたい場合には、まとめた資料を無料で公開しているのでご自由にお使いください。
無料公開中の資料はこちら
①導入するときの手続き(電力協議や申請)で失敗する
まずは、完全自家消費型の場合の注意点を解説します。
予算の都合で、導入時期をある程度決められていると思います。導入時期にあわせるために電力会社への協議や申請時期を知る必要があります。
完全自家消費型で系統 (電線網)に電気を流さず自家消費する場合でも電力会社と協議をおこなう必要があります。
そして申請許可が出てからでないと、工事を進めることができません。
この申請許可は、1ヵ月~6カ月程度かかります。(電力会社によって異なります)
完全自家消費で電気が余らない自家消費型の太陽光発電でも、各電力会社への協議申請は必須となります。
次に、余剰分売電をする場合の注意点を解説します。
※余剰売電とは、太陽光発電で使い切れなかった電力を売ること
FITの場合は50kWで低圧と高圧に分かれて、 低圧は事前協議が免除されています。
しかし、高圧受電設備(キュービクル)を介してグリッドに逆潮流する場合は、 設備容量が50kW未満でも高圧扱いとなります。
電力のシステム設計をする前に、電力事前協議にて送電網の空きがどうかを確認が必要です。
空きがあるとなった場合、余剰の電力システム設計ができるようになります。
事前協議なしで現場調査、システム設計をしても空きがなければ余剰を送電網に流すことができないため、注意してください。
②補助金のことをよく理解していなくて失敗する
令和5年度も昨年度に引き続いて太陽光発電に活用できる補助金が出る予定ですが、
補助金申請内容をよく理解しないまま設置の話を進めてしまうと失敗してしまいます。
例えば、環境省のストレージパリティ補助金を利用したい場合、産業用蓄電池の導入が必須となりました。
それに対し、産業用蓄電池の導入が必須ではない地方自治体の補助金が実施される場合があります。
産業用蓄電池は導入費用が高額になるため、産業用蓄電池と一緒にして環境省の補助金を活用した方がメリットが高いのか、
蓄電池をつけずに地方自治体の補助金を活用した方がメリットが高いのか、比較することが大切です。
余剰売電についても注意が必要です。
現在、太陽光発電は自家消費が対象となりますが、完全に売電ができないわけでありません。
FIT/FIP制度を使わなければ余剰売電が可能な場合が多く、例えば、電気代削減以外に遮熱効果を狙って、なるべく屋根全体にパネルを設置したい場合、
「自家消費+FIT以外の売電」として補助金申請する手段もあります。
それ以外にも、補助金の完了報告の期限についてのトラブルがあります。
通常は年度内に工事の完了・施工店への支払いを済ませ、工事後の写真や支払いの領収書等を含めた完了報告を提出する必要があります。
完了報告を期限までに提出できなければ、採択が取り消しになってしまう場合があります。
補助金の情報が入ると、補助率や上限額に目が行ってしまい、細かいところに気が付けないことが多いです。
検討を進めていく中で、こんなはずではなかったとならないよう、最初の段階でしっかりと施工業者から説明をしてもらいましょう。
また、その段階で、施工業者自身が補助金について詳しくなさそうであれば、他の施工業者にも話を聞いて、比較することをお勧めします。
③構造計算や耐荷重確認をせずに導入して失敗する
特に古い建物(築30年が目安)の場合は、太陽光パネルが載せられるかどうかの確認が必要です。
建物が太陽光パネルの重さに耐えられずに、屋根が壊れてしまう危険性があります。
特に古い建物の場合には構造計算をして、太陽光パネルを載せても問題ないか確認できれば安心です。
太陽光パネルの設置自体が長期荷重となり、さらには設置期間が20年以上となる場合が大半です。
もしも太陽光パネルの設置を検討していて建物に不安がある場合は、必ず建築士に相談してください。
太陽光パネルを載せる前に、構造計算の依頼をしておくことが安心です。
④施工で必須となる「停電工事」で失敗する
太陽光発電では、停電工事が必要です。
この停電工事にも注意点があります。停電工事前と工事期間中の注意点を解説します。
まず、停電工事の前に、停電があることを社内で共有します。
そして、施設の警備をしている警備会社に連絡をして停電になることを伝えます。
とくにテナントがある施設では、停電情報を共有しておくと停電作業がスムースに実施できるように調整が必要です。
逆に、停電工事を共有していないと、お客様にご迷惑をおかけしてトラブルの原因になります。
事前に必ず確認してから進めてください。
次に、停電工事中の注意点を解説します。
停電させる直前、停電復旧時は社内で共有しておきます。
停電の直前には、電気主任技術者や電気工事士に状況を確認して、 およその停電時間も報告します。
停電時間が長時間かかるわけではないですが、その間は業務を進めることができないので、きちんと事前に共有が必要です。
停電時に思わぬトラブルとならないよう、事前にできることはすべておこなってください。
⑤設置後に保安管理維持で失敗する
太陽光発電は、出力により、50kWを境に扱いが異なります。
50kW以上の太陽光発電設備は、重大な事故につながる危険があるため、保安には主任技術者の選任が義務付けられています。
年2回、主任技術者による定期点検が義務付けられており、保安管理費用を経費として考えておく必要があります。
大規模な太陽光設備にすると、その分高額になりますが、主任技術者の中には太陽光発電や蓄電池への理解が不足していることもあり、必要以上に高額な見積りが出ることもありますので、注意が必要です。
※毎月のイニシャルが発生主任技術者による保安管理費用 (太陽光追加分) どのように設備を接続するのか、 保安上問題 はないかなど、 主任技術者との協議が必要となります。
50kW未満の太陽光発電についても、保安管理は必要です。
まず、事故報告です。
10kW以上50kW未満の太陽光発電については、2021年4月から事故報告が義務化されています。
【報告が必要な事故】
・感電事故:感電により人が死亡もしくは入院した場合の事故
・電気火災事故:太陽光パネルなどの設備が原因で発生した火災
・他者への損害:太陽光パネルの飛散等で、他者へ損傷が発生する事故
・設備の破損:太陽光パネルの破損等で運転が停止する事故
事故報告は、各地域を管轄している産業保安監督部(関東なら「関東東北産業保安監督部 電力安全課」)に対し、所有者が24時間以内に速報を報告、さらに30日以内に詳細の報告をする必要があり、
報告をしなかった場合、もしくは虚偽報告をした場合は罰則の対象となります。
さらに、2023年3月から、10kW以上50kW未満の太陽光発電に対しても保安管理が強化され、新たに3つの義務を負うことになります。
【新たに発生する3つの義務】
・技術基準適合維持
・基礎情報提出
・使用前自己確認
提出する基礎情報については、保安管理担当者も報告項目に含まれており、社内で対応できなければ委託する必要があります。
太陽光発電設備が増えてきていますが、それと同時にずさんな工事、保安管理の不備により放置されている設備が増えてきています。
そういった理由から、重大な事故につながる恐れがあるため、保安管理に対しての規則が厳しくなってきています。
保安管理については、新設時だけではなく、既設も対象になることがあり得ますので、注意が必要です。
太陽光パネルの設置には、このほかにも多数の注意点があります。
続きは順次公開しますので、お待ちください。
先に内容が知りたいという場合は、お問い合わせください。
近隣エリアで、中小企業が使える補助金一覧
近隣エリアが出している補助金を探している場合は、エリア別の補助金や助成金の一覧をご覧ください。
本社や支店の事業所があれば、使える補助金が見つかります。
- 令和6年度版:全国の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:東京都の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:神奈川県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:千葉県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:埼玉県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:茨城県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:栃木県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:群馬県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:福島県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:新潟県の中小向け企業補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:大阪府の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:福岡県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 中小企業経営強化税制(税制優遇制度)で即時償却や税額控除
もしも見つからなかった場合や探すのが面倒な場合は、明電産業の無料相談をご利用ください。
【設備別】中小企業が使える補助金一覧
省エネや再エネ設備など、設備ごとに補助金を探している場合は、設備別の補助金や助成金の一覧をご覧ください。
本社や支店の事業所があれば、使える補助金が見つかります。
- 令和6年版:中小企業が省エネ・再エネ・畜エネ・創エネ設備に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業が太陽光発電設備に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業が蓄電池に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業がLED照明への交換に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業が業務用エアコン交換に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業が変圧器(キュービクル/受変電設備)に使える補助金・助成金一覧
- 令和6年版:中小企業がEV・PHV用充電器に使える補助金・助成金一覧
- 中小企業経営強化税制(税制優遇制度)で即時償却や税額控除
もしも見つからなかった場合や探すのが面倒な場合は、明電産業グループの無料相談をご利用ください。
明電産業グループは、昭和23年創業(栃木県宇都宮市)の電設資材の商社です。
部材の仕入れも、施工(工事)も、補助金や税制優遇制度の申請サポートもできます。
補助金を使って、設備の導入費用を削減したい場合は、まずはお気軽にご相談ください。
【事例紹介】補助金を使ったコスト削減
設備ごとに、補助金を使った事例を画像や動画付きで掲載しています。
きっとお役に立てると思いますので、ご覧ください。
補助金を使った場合の初期投資費用や投資回収期間を記載しています。
これから設備投資や補助金活用をご検討の場合は、ご覧ください。
明電産業グループでは、あなたの会社の脱炭素経営や環境対策、SDGs活動の取り組みを無料でPRします。
自社の活動をWEBサイトやSNSでPRしたいけど、自社では難しい場合はご連絡ください。
必要に応じてドローン撮影をおこないます。画像や動画素材はすべて無料で提供します。
中小企業のSDGs取り組み事例を募集します!
よくあるご質問(Q&A)のまとめ
明電産業グループでは、設備投資や補助金についてお客様からのご相談やご質問をいただきます。
太陽光発電設備/蓄電池/LED照明/省エネ空調/受変電設備(キュービクル)/EV充電器/税制優遇制度について、Q&Aをまとめていますのでご覧ください。
お客様からの「よくあるご質問」を見る
「よくあるご質問(Q&A)」で解決できない場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
明電産業グループの補助金申請の専任がお答えします。
設備の導入コストや投資の回収期間を大幅に削減したいなら、ご相談ください

法人企業が補助金を活用すれば、大幅なコストダウンができます。
明電産業グループは、昭和23年創業(栃木県宇都宮市)の電設資材の商社です。
当社では、設備の仕入れ・施工・補助金の申請まで一括で対応いたします。
補助金を使うことが前提なので、設備の導入コストを大幅に削減できます。
もしも次の内容に当てはまっていたら、補助金を検討してください。
- 設備導入に費用をかけたくない
- 補助金や助成金を探すのが面倒だ
- 施工や補助金申請など、まとめて依頼したい
- 補助金の実績があるところに頼みたい
- 補助金が決まるまでは、お金を払いたくない
補助金申請のポイントは、今すぐ準備をすることです。
理由は、補助金の予算が達成してしまうと受付終了となるからです。
明電産業グループの経験では、たったの3時間で早期終了した補助金もあります。
もしもあなたが、設備の導入コストを削減しつつ、業務の手間を省き、実績のある会社を選びたいのならまずはご相談ください。
ご自身で調べるより、ご相談いただいた方が早く見つけられます。
一緒に、あなたの会社で使える補助金を見つけましょう。