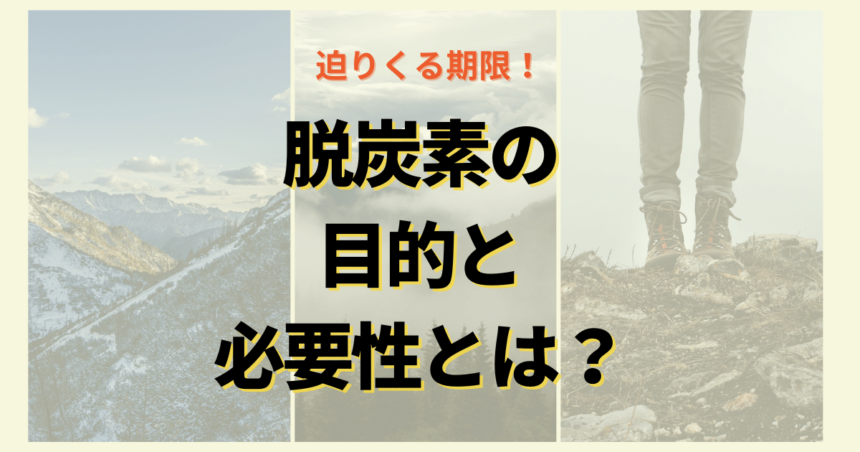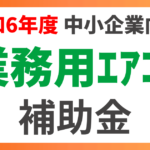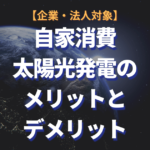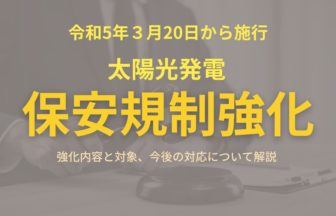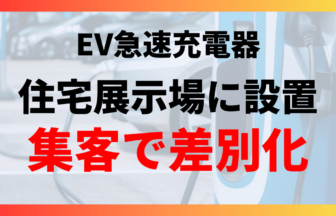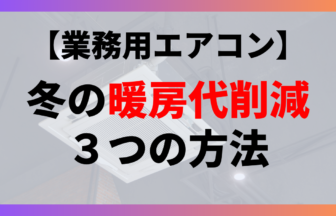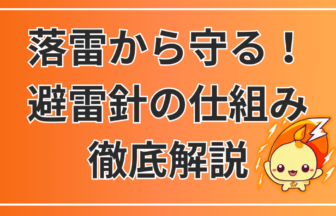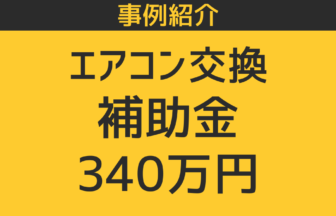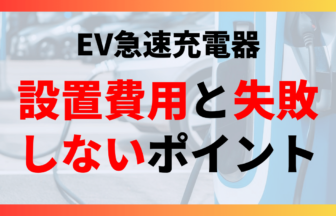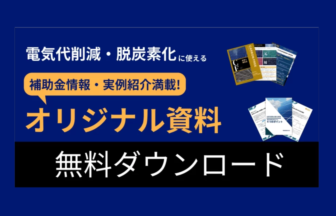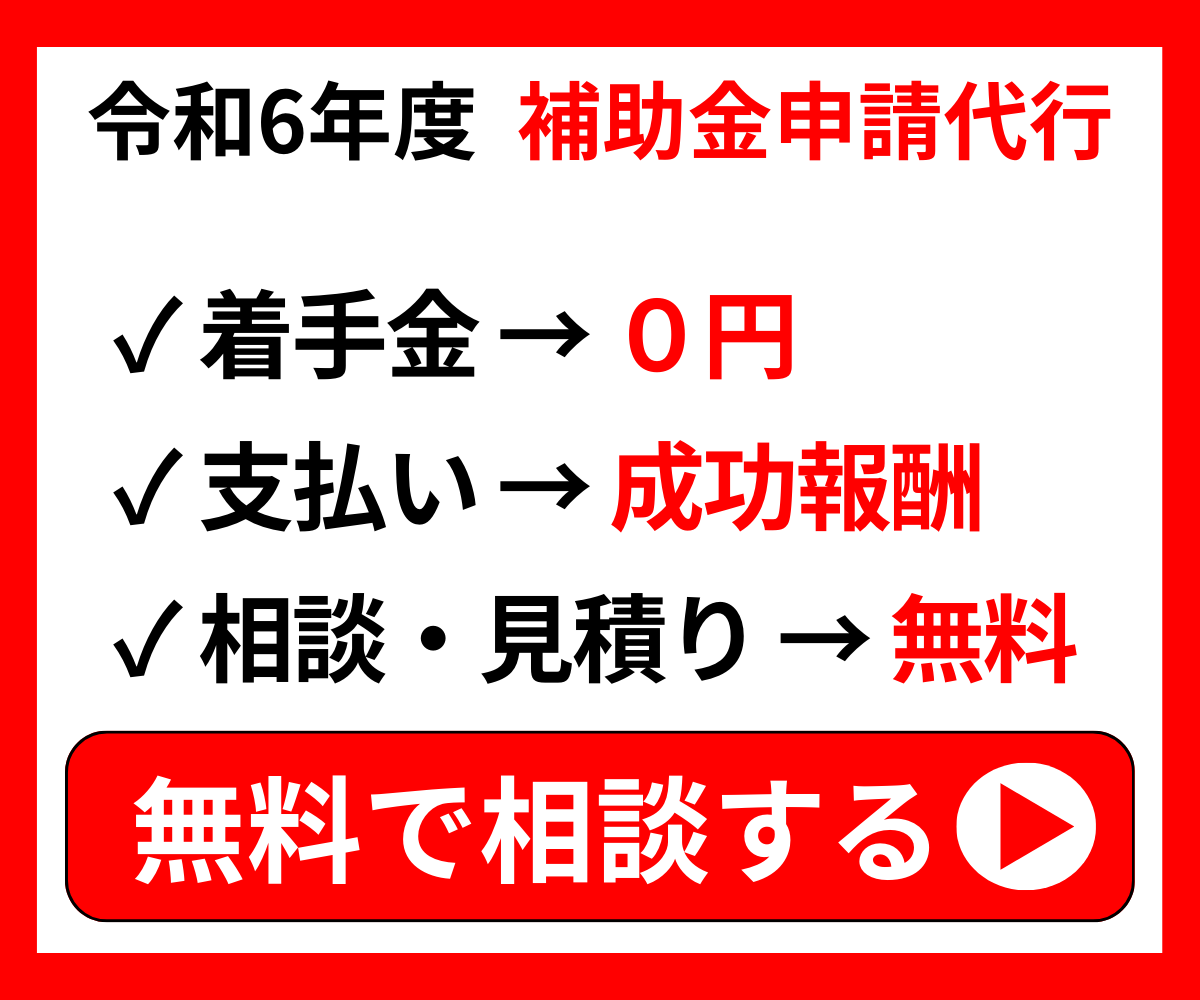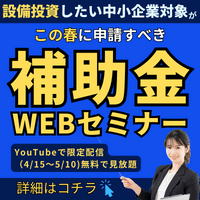2015年に世界平均気温の上昇を2℃未満に抑えることを目的としたパリ協定が採択されました。
各国は温暖化の原因であるCO2を削減する目標期限を2030年に設定し、その目標達成に向けた動きを加速させています。
この動きはあなたの会社が生き残る上で、とても大きな影響があります。
この記事では、企業にとっての脱炭素化の目的と必要性を解説します。
CO2削減は、売上拡大や融資に必要条件になる
現在、グローバル企業を中心としてRE100(事業運営を100%再生可能エネルギーで調達する取り組みの枠組み)や SBT(温室効果ガス削減目標の指標)等、脱炭素経営に向けた企業の取り組みが急速に広がっています。
この流れを受けて、直接的な事業活動に伴う温室効果ガスの排出のみならず、原材料・部品調達の段階も含めた排出量を削減する動きや、金融機関の融資先の選定基準に地球温暖化への取り組み状況が加わるケースが増えています。 中小企業にとっても、CO2排出削減が光熱費・燃料費削減という「守り」の要素に留まらず、売上拡大や金融機関からの融資等「攻め」の要素を持ってきていると言えます。
投資家の関心
多くの企業にとって自社への投資を呼び込むことは重要ですが、お金の出し手である投資家が脱炭素への関心を高めていることは、重要な背景となっています。 2020年頃から、機関投資家は脱炭素への投資姿勢を明確化、欧米の金融機関では毎月のようにカーボンニュートラルへの投資を明らかにしており、ゴールドマン・サックス・グループやシティグループ、JPモルガン・チェースなどが投資先の気候リスクを判断、石炭産業への融資を停止しています。
当然ながら日本でも同様の動きが出ており、厚生年金と国民年金の積立金を管理・運用している年金積立金管理運用独立行政法人は、2017年から「環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)」を重視したESG指数に連動する投資を進めています。
消費者の意識変化
近年の消費者の意識変化は、これまでの流れと一線を画しています。これは環境問題に限らず、差別やジェンダーの問題等についてもSNS等で批判が集まるケースがあるように、単純に「社会貢献をしよう」「世の中に良いことをしよう」という漠然としたものから、企業の個々の対応や姿勢に具体的に批判が向けられるようになりました。
例えば、三菱商事等が計画していたベトナムの石炭火力発電所のプロジェクトは、環境活動家による見直しの要請が発端となり、プロジェクト撤退を決定。 また東芝や三井物産も火力発電所の新規建設から撤退表明する等、こうした流れを受け石炭火力離れは加速しています。
この様に企業としてSDGsを掲げていても、石炭火力発電に関する取り組みが進まないことで批判を集めるように、企業の具体的対応に対し厳しい目が向けられるようになっています。
消費者の意識変化も、企業が脱炭素への取り組むべき要因の1つでしょう。
炭素税の本格導入
2021年3月、環境省がCO2排出量に応じて企業に税を課す炭素税の本格的導入検討が報道されました。
日本では既に2012年から「地球温暖化対策のための税(温対税)」が導入されていますが、欧州各国では1トン当たり数千円~1万円の税率であるのに対し、日本は289円と限定的なものに留まっています。
具体的な時期や制度は未定ですが、炭素税の本格的導入で今後企業にとっては環境負荷に対して様々な規制が強まっていくことが予想されます。
最後に
脱炭素は2030年に向けて世界中で加速するのは間違いありません。
それに伴い、企業の評価、他社との取引に影響が出ることが予想されます。
政府、自治体共に、脱炭素への取組を促進するために補助金を実施してますので、あなたの会社において、脱炭素化を進めていきたいと考えているようであれば、実際に見積等を取る前に私たちにお問い合わせいただければと思います。
近隣エリアで、中小企業が使える補助金一覧
近隣エリアが出している補助金を探している場合は、エリア別の補助金や助成金の一覧をご覧ください。
本社や支店の事業所があれば、使える補助金が見つかります。
- 令和6年度版:全国の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:東京都の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:神奈川県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:千葉県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:埼玉県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:茨城県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:栃木県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:群馬県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:福島県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:新潟県の中小向け企業補助金・助成金の一覧
- 中小企業経営強化税制(税制優遇制度)で即時償却や税額控除
もしも見つからなかった場合や探すのが面倒な場合は、明電産業の無料相談をご利用ください。
明電産業グループは、昭和23年創業(栃木県宇都宮市)の電設資材の商社です。
商社の強みを活かして低価格で部材の仕入れや施工をおこないます。
さらに、補助金の活用を前提にしていますので、設備の導入コストや投資回収の期間を大幅に削減できます。
もしもあなたの企業や事業所が、東京都、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、福島県にあって、補助金を使って設備投資や電気代削減、脱炭素経営を目指したい場合は、まずはご相談ください。
【事例紹介】補助金を使ったコスト削減
設備ごとに、補助金を使った事例を画像や動画付きで掲載しています。
きっとお役に立てると思いますので、ご覧ください。
補助金を使った場合の初期投資費用や投資回収期間を記載しています。
これから設備投資や補助金活用をご検討の場合は、ご覧ください。
明電産業グループでは、あなたの会社の脱炭素経営や環境対策、SDGs活動の取り組みを無料でPRします。
自社の活動をWEBサイトやSNSでPRしたいけど、自社では難しい場合はご連絡ください。
必要に応じてドローン撮影をおこないます。画像や動画素材はすべて無料で提供します。
中小企業のSDGs取り組み事例を募集します!
よくあるご質問(Q&A)のまとめ
明電産業グループでは、設備投資や補助金についてお客様からのご相談やご質問をいただきます。
太陽光発電設備/蓄電池/LED照明/省エネ空調/受変電設備(キュービクル)/EV充電器/税制優遇制度について、Q&Aをまとめていますのでご覧ください。
お客様からの「よくあるご質問」を見る
「よくあるご質問(Q&A)」で解決できない場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
明電産業グループの補助金申請の専任がお答えします。
設備の導入コストや投資の回収期間を大幅に削減したいなら、ご相談ください

法人企業が補助金を活用すれば、大幅なコストダウンができます。
明電産業グループは、昭和23年創業(栃木県宇都宮市)の電設資材の商社です。
当社では、設備の仕入れ・施工・補助金の申請まで一括で対応いたします。
補助金を使うことが前提なので、設備の導入コストを大幅に削減できます。
もしも次の内容に当てはまっていたら、補助金を検討してください。
- 設備導入に費用をかけたくない
- 補助金や助成金を探すのが面倒だ
- 施工や補助金申請など、まとめて依頼したい
- 補助金の実績があるところに頼みたい
- 補助金が決まるまでは、お金を払いたくない
補助金申請のポイントは、今すぐ準備をすることです。
理由は、補助金の予算が達成してしまうと受付終了となるからです。
明電産業グループの経験では、たったの3時間で早期終了した補助金もあります。
もしもあなたが、設備の導入コストを削減しつつ、業務の手間を省き、実績のある会社を選びたいのならまずはご相談ください。
ご自身で調べるより、ご相談いただいた方が早く見つけられます。
一緒に、あなたの会社で使える補助金を見つけましょう。